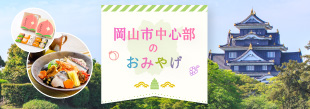2011年に「ご当地グルメでまちおこしの祭典!第6回B-1グランプリin姫路」で、「ひるぜん焼そば好いとん会」がゴールドグランプリを受賞したことから注目を集めた、ひるぜん焼そば。
2011年に「ご当地グルメでまちおこしの祭典!第6回B-1グランプリin姫路」で、「ひるぜん焼そば好いとん会」がゴールドグランプリを受賞したことから注目を集めた、ひるぜん焼そば。
そのはじまりは、昭和30年代のこと。県北屈指の高原地帯である蒜山(ひるぜん)高原では、冬の保存食として各家庭で作られていた味噌を使った焼きそばやジンギスカンが食べられていました。ある時、地元の「ますや食堂(現在は閉店)」のおばちゃんが、ニンニクや玉ねぎ、リンゴなどをあわせた味噌だれに、親鶏のかしわ肉と蒜山の特産であるキャベツを入れて作った焼きそばが評判となり、「ひるぜん焼そば」として定着したのだそうです。
必須の具材は、特製だれと焼きそば、鶏肉、キャベツの4つ。鶏肉は親鶏を使うのが元祖ですが、柔らかく食べやすい若鶏を使っても大丈夫。甘辛い味噌だれに、箸が止まらないおいしさです。
<<参考>>
焼肉店や道の駅など、「ひるぜん焼そば好いとん会」公認店の9店舗(2022年3月現在)で味わえます。「ひる(昼)ぜん」に対抗して考えた、「あさぜん焼そば」「よるぜん焼そば」といった、発祥の地ならではのおもてなしも。詳しくはこちらのWEBサイトをご覧ください。




 津山市周辺は飛鳥時代頃から牛馬の流通拠点であったという史実があり、牛肉を含めた獣肉を食べるのが禁止されていた江戸時代にも、津山藩の領内では特例として牛肉食が江戸幕府に許可されていたといわれています。「養生食い(ようじょうぐい)」という、滋養強壮の食材として牛肉を食べる文化があったことが理由ですが、農耕や輸送だけでなく食用としても、人々の生活に欠かせない存在だったようです。
津山市周辺は飛鳥時代頃から牛馬の流通拠点であったという史実があり、牛肉を含めた獣肉を食べるのが禁止されていた江戸時代にも、津山藩の領内では特例として牛肉食が江戸幕府に許可されていたといわれています。「養生食い(ようじょうぐい)」という、滋養強壮の食材として牛肉を食べる文化があったことが理由ですが、農耕や輸送だけでなく食用としても、人々の生活に欠かせない存在だったようです。 笠岡市は古くから養鶏と製麺が盛んであり、瀬戸内海に面していることから海の幸にも恵まれています。その土地柄を活かして、戦前から鶏がらスープと煮鶏(鶏チャーシュー)を使った中華そばが親しまれてきました。
笠岡市は古くから養鶏と製麺が盛んであり、瀬戸内海に面していることから海の幸にも恵まれています。その土地柄を活かして、戦前から鶏がらスープと煮鶏(鶏チャーシュー)を使った中華そばが親しまれてきました。 サワラやママカリ、シャコといった瀬戸内の海の幸と、旬の野菜を盛りつけた華やかなちらし寿司。お祭りやお祝いのときなど、ハレの日に食べる郷土料理として愛されていますが、こちらも歴史にまつわる誕生秘話があります。
サワラやママカリ、シャコといった瀬戸内の海の幸と、旬の野菜を盛りつけた華やかなちらし寿司。お祭りやお祝いのときなど、ハレの日に食べる郷土料理として愛されていますが、こちらも歴史にまつわる誕生秘話があります。 この真っ黒なチャーハンのようなものを初めて見たとき、「これ、おいしいの・・・?」と思う方はきっと多いのではないでしょうか。
この真っ黒なチャーハンのようなものを初めて見たとき、「これ、おいしいの・・・?」と思う方はきっと多いのではないでしょうか。 瀬戸内海に面した岡山県南部の地域はかつて漁業で栄えていた町が多く、現在も魚介の新鮮さや質の高さで知られる漁港での漁が活発です。その一つが、浅口市にある寄島(よりしま)漁港。
瀬戸内海に面した岡山県南部の地域はかつて漁業で栄えていた町が多く、現在も魚介の新鮮さや質の高さで知られる漁港での漁が活発です。その一つが、浅口市にある寄島(よりしま)漁港。